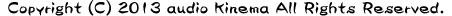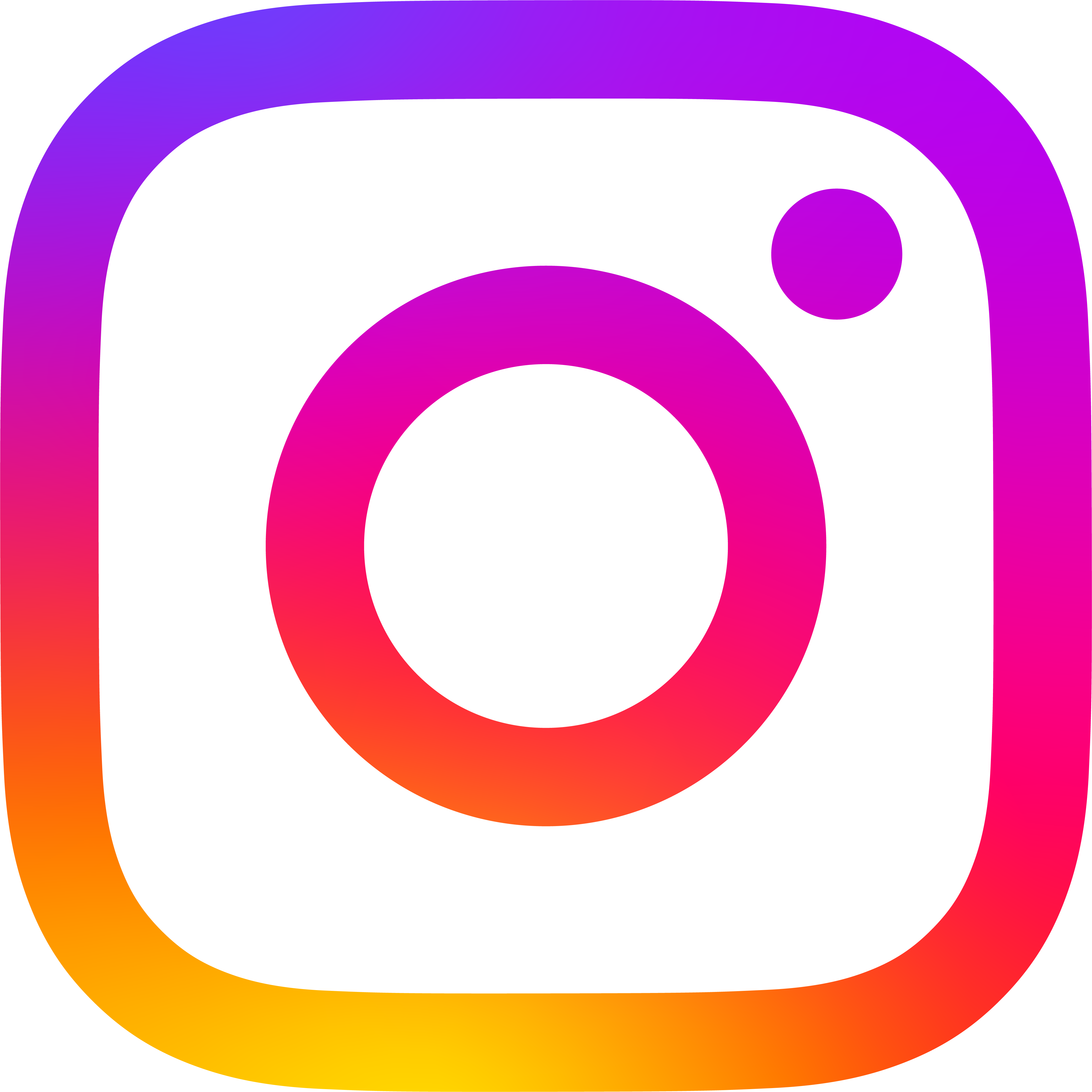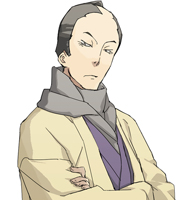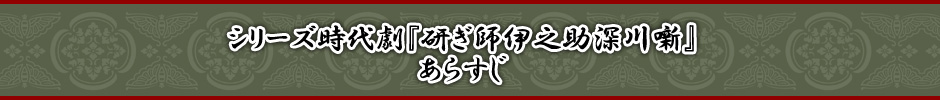
安政二年、武家政権にも暗雲が漂い始め、この五年後には江戸城桜田門外にて大老井伊直弼が暗殺されるという徳川幕府終焉間近のある秋の日。
深川、海辺大工町(うみべだいくちょう)の裏長屋、次郎兵衛店(じろべえだな)で船大工を相手に研ぎ屋をしている伊之助の元に、笹野平五郎と名乗る旅姿の浪人が、刀の研ぎを頼みに現れた。それは、生々しい死闘の痕が残る刃こぼれした大刀(だいとう)だった。刀剣の類の研ぎは金輪際やらないと断って久しい伊之助だったが、朴訥な平五郎の澄んだ人となりにその依頼を断ることができなかった。なによりこの男が、平素より懇意の間柄である円妙寺の願海和尚の紹介であったからだ。
仕上がりまでの間宿無しの平五郎を、伊之助は麻布にある江戸随一と評判の直心影流男谷道場へと連れていく。そして、道場主の男谷精一郎(おだにせいいちろう)へ平五郎を預かってくれるよう頼むのだった。剣聖と世に知られた男谷精一郎と親しげな伊之助に驚きを隠せない平五郎。伊之助とは一体何者なのか・・・?
さて、そんな伊之助のところへ、今度は女剣士浅田留伊(あさだるい)が、供の者二名とともに現れた。彼女もまた願海和尚の名を出し、一通の文を差し出した。それは、和尚から伊之助へ宛てた添え文だった。そこには次のことがしたためられていた。
留伊は、実父浅田忠左衛門を殺害した敵(かたき)を求めて仇討ちの旅をしているという。そしてその敵とは、何とあの笹野平五郎だというのだ。信じられない和尚だったが、その殺しには目撃者もあったというのだ。そして国を出奔した平五郎を追って、助太刀の稲葉大輔、下女のお梅と共にこの円妙寺へたどり着いたのだった。留伊の本懐は、父が惨殺された時に手にしていた形見の大刀で、必ずあの憎き平五郎を討ち取ることだと和尚に語ったことが記されていた。和尚は手紙の最後を、しかし、自分はどうしても平五郎を疑うことができないと締めくくっていた。
文を閉じた伊之助に、留伊もまた父忠左衛門の刀の研ぎを伊之助へ依頼する。見ると、その大刀にも刃こぼれがあるのだった。その時伊之助は、その刃こぼれが重要なことを語っているのを、研ぎ師の勘で見逃さなかった。そして同時に、平五郎の罪に疑問を抱くのだった。
伊之助はただならぬ二人の因縁を感じて、この刀も預かることにする。そして留伊たち一行を、近所の一膳飯屋「あかね」の主人に頼み、二階の空き部屋へ滞在させるのだった。笹野平五郎に浅田留伊。伊之助はかれらの身に起こっている出来事に不安を覚えずにいられなかった。
ふた振りの刀から始まった謎にはまり込んでゆく伊之助。この仇討ちの裏に隠されたものとは一体何なのか。忠左衛門の死の真相は、やがてかれらを巻き込む陰謀へと繋がっていくのだった。御用聞きの辰吉親分や剣客男谷清一郎など仲間の助力を得て、伊之助はしずかに忍び寄る不気味な闇に立ち向っていく・・・。

裏長屋、次郎兵衛店の住人たち


船大工の大工道具の研ぎ師。
一人暮らしの伊之助は、毎朝六ツ半(朝7時)には、近所のおせき婆さんが拵えた朝餉を食べ終え、研ぎの仕事をはじめるのが日課となっている。
夕食は、近くの一膳飯屋「あかね」で済ますのが常となっている。


伊之助と同じ次郎兵衛店に住む未亡人。
毎朝、伊之助の長屋へ来ては朝飯をつくり、一日をそこで過ごしている。
とにかく世話焼きの噂好きという、何にでも首を突っ込む裏長屋の名物婆さん。
伊之助の隣の店に住む船大工。
根はいいがどこか頼りないところがある。お峰を妻に持つ新婚夫婦。
又六の女房で身ごもっている。しっかりと夫を支える快活な女性。


次郎兵衛店へ移り住んだ新参者。娘の多江(たえ)と二人暮らし。
もとは芸者の身の上。
その美しさから男たちの熱いまなざしを浴びている。
伊之助の仲間たち
男谷道場の一番弟子。
清廉潔白な気質で、毎日を剣術と向き合って過ごしている。


定町廻同心、山名伊織の配下として深川を縄張りに働いている御用聞き愛称は「深川の辰吉親分」 実直な性格で土地(ところ)の信頼も厚い。
女房のお銀に料理屋「辰美」を経営させている。
奥州から来た人たち
留伊の父親。留伊のまだ幼いときに、藩に禄を返上し隠居の身になる。
本田道場の門弟。水野、保田の弟弟子にあたる。
その他の人たち